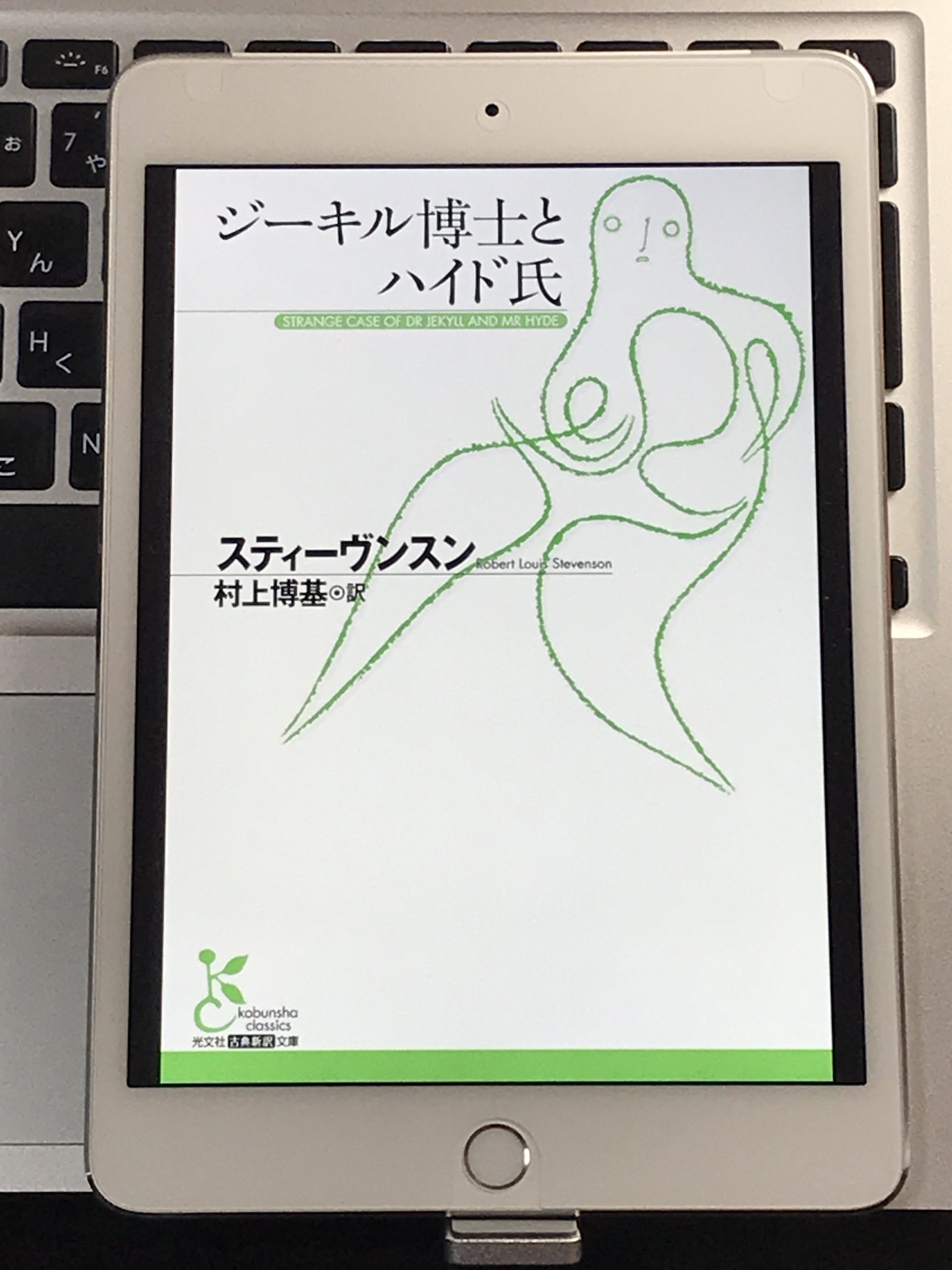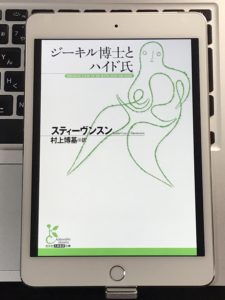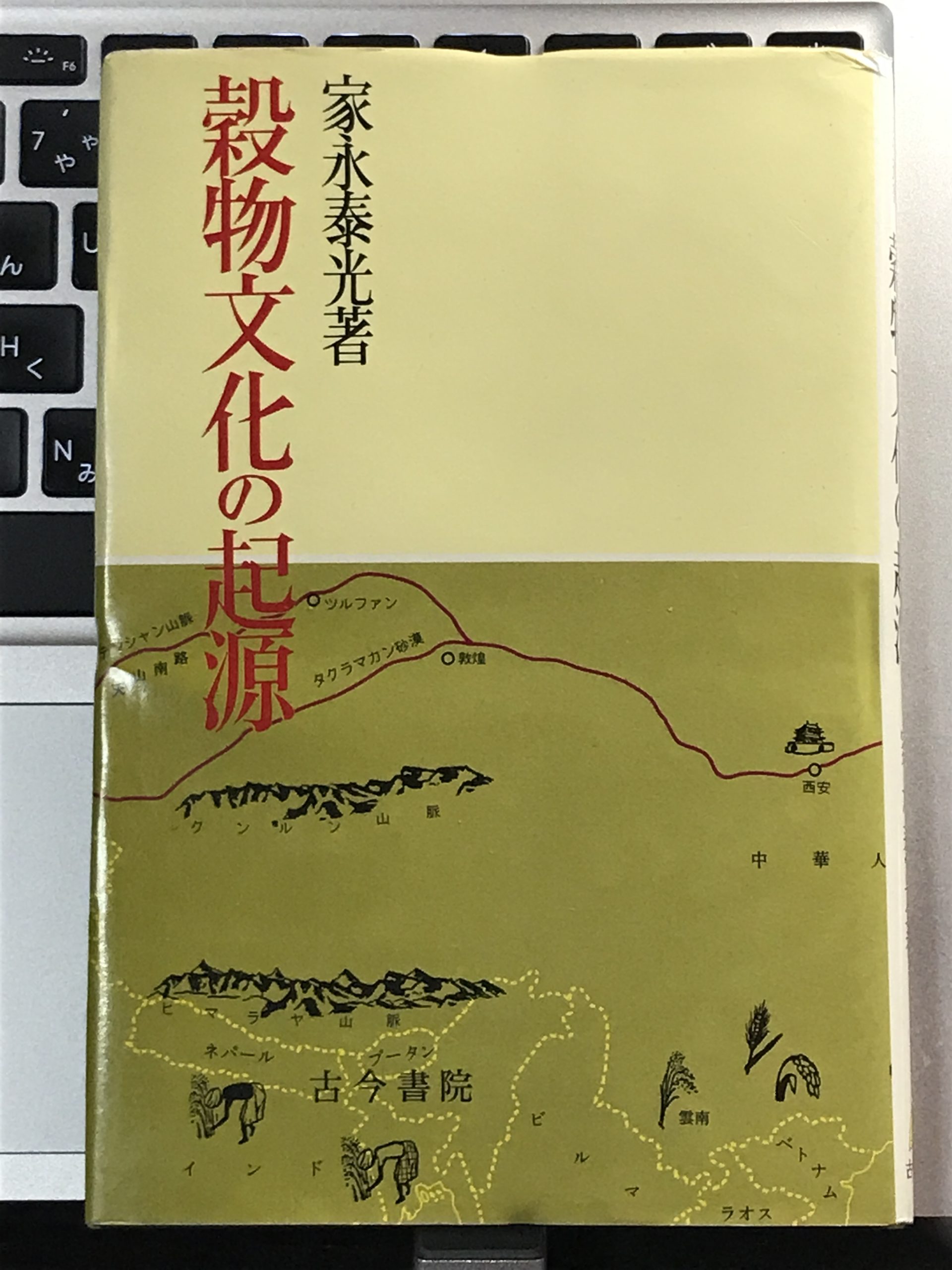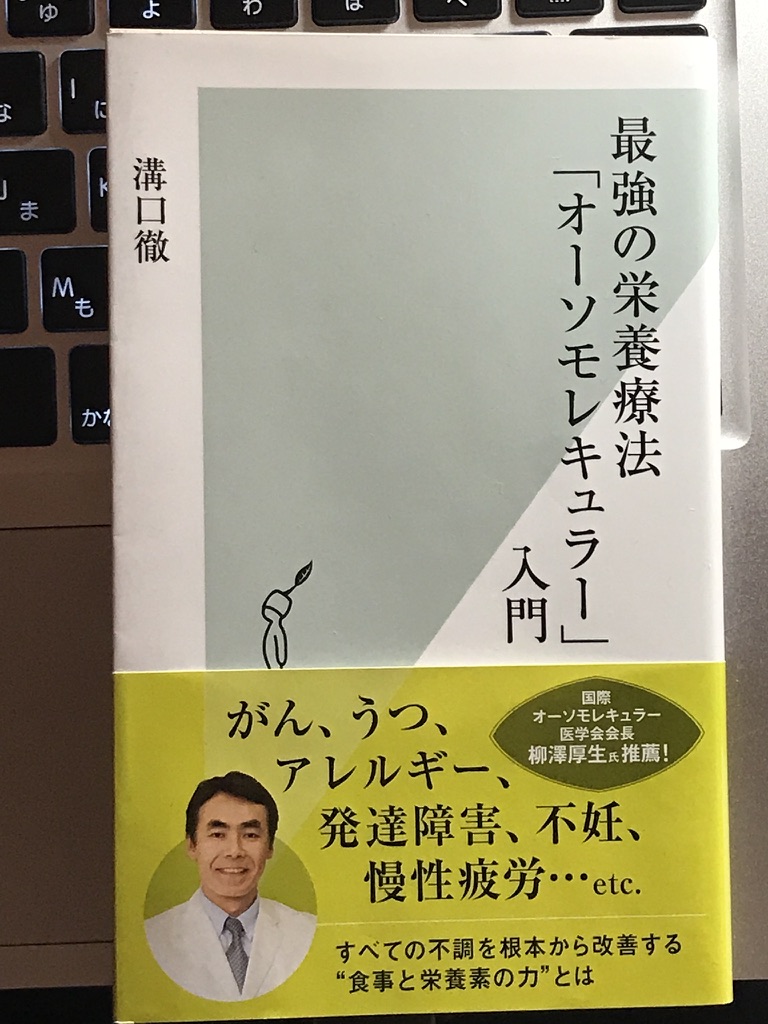※あまりにも有名な作品ので、ややネタバレ的なことも書いてあります。
有名だけど自分で読まない物語の代表格
本書巻末に記載されている「解説」にも言及があるように、”あまりにも有名すぎて、かえって読まれることの好少ない名作”のひとつとして本書『ジーキル博士とハイド氏』がその一典型とされています。
まさにその通りで「ジキルとハイド」といえば二重人格の代名詞だと思う、それほど人口に膾炙している、もはや慣用句と言えるほどのものです(かつて「ジキル」が多かったようですが著者が言う発音である「ジーキル」が現在では一般的になっています)。
なお、ジーキル博士(Dr. Jekyll)はフランス語の「Je」と英語の「kill」を組み合わせた「われ殺す」の含意を持つとよく言われており、一方のハイド氏(Mr. hyde)は「隠れる男」とすぐ連想できるような名前とされています(本書の解説より)。
ジーキル博士は医学者、医者であり人命を救う立場でありながら、心の中にはハイド氏に象徴されるような欲望や悪意に満ちた部分も持っており、救命者であると同時に殺人者であるというのが、読んだ後になるとなんだか納得するような。
私のような浅い本読みではこんな感じの解説を読むだけでも作品を深く読んだような感じなるから安上がりだなあと思います。解説や翻訳をするだけの人の頭の中は、一般人とは作りがちがうのだなあと改めて認識。
この本の訳者である村上氏も、本作の翻訳を打診されたときには未読であったというほどこの作品は有名なのに読まれなという「名作らしさ」を見せつけてくれています。
それだけ広く人々に知られ、二重人格の人物を表す慣用句としても定着している本作ですが、やはり自分で(訳文とはいえ)その物語を追ってみると、作品が持つなんとも言えぬ不気味さや暗さ、そしてその怪しい雰囲気に引き付けられる感じを体感できます。
これは読まずにいるのはもったいないほどに知的な興奮にも似た興味をそそる力が宿っている、そんな作品だと言うことができるでしょう。
読む前からあまりにも有名だから、あえてここで手に取って読んでみようと思う人が少ないということは、この作品を前にしたときの心境を思えば当然のことと思います。
しかしそこで、名作には自分であたってみると言う姿勢を持って読んでみると、たとえ物語の柱がどうなっているか知っていたとしても、そこに至るまで、それが明らかになるまでのプロセスを味わう楽しみは失われてはおりません。
むしろボンヤリと中途半端に知っているがために、早くそのモヤモヤした半端な理解をはっきりさせたい、といミステリー小説を読むときの心境を持ちつつ、読み進めるごとに深く物語の中に引き込まれていく、そんな作品でもありました。
人間が持つ善と悪、二面性が拗れた末の二重人格
このお話は品行方正で非の打ちどころのない人物であるジーキル博士が、時に凶悪な要素を持つハイド氏になってしまう、ということから「二重人格」がテーマの物語かと思われているところがあります(私がそう思っていました)。
それも間違いではないのですが、結果的に同一人物の中にある善と悪が分離するような薬を生み出し、それを使ってジーキル博士が今まで戦ってきた「悪の面」を切り離してしまおうとしたところが発端になります。
アラフォー世代なら知っている人も多いであろう「ドラゴンボール」に出てくる、ピッコロと神様が分離したような感じ(ピッコロの分離はジーキル博士とハイド氏の分離を真似したのでしょうか)でもあります。
悪を追い出したというよりは、これまで抑圧してきた悪の面(=表の世界で生きている時間が短いもう1人の自分)を分離させる過程で明確になり、秘密の薬剤によりそれと人格が入れ替わってしまうというお話。
骨格も含めて待ったく別人になってしまうところが、ファンタジーな小説らしい世界のことなのではあります。
その変身するシーンやそんな二重人格のよな状態に至るまでの過程をジーキル博士自身が語って明らかになる箇所では、その淡々とした口調に薄気味悪さすら感じます。
物語に入り込んでいる時には、自分の中の善悪に二面性(あるいは建前と本音)の対立に意識を向けざるを得なくなります。
そんな自己の内省をも読みながら促すというところに、この物語が長い時を超えてもいまだに読み継がれ、そして古典作品となった今でも慣用句や代名詞のような扱いを受けるようになったのだなあと感じました。
本音を抑圧しすぎないように生きよう
この作品を読んだからと言うわけではないのですが、ただ自分のこれまでの人生において、周囲からの評価を気にしすぎて「優等生」ぶりすぎてはいないか?という自省をするきっかけになりました。
実際にジーキル博士がハイド氏になってしまうような、別人として抑圧している負の欲望を解放することにならないでしょうが、あまりにも自分の本質とかけ離れた人生を生き続けていたら、晩年になって大きな後悔を抱えることになるかもしれません。
この本の主要人物たるジーキル博士自身、本当の自分を抑圧し、周囲や社会が評価する自分像を作り上げ、それを磨き上げることを優先し続けた結果、本当に自分が望んでいる自由な人生を蔑ろにしてきてしまったようにも思えます。
そして長年の間、抑圧してないものと扱ってきた本音の部分が、元々は自由さを求めていただけのものが、時間の経過とともに抑圧に対する憎悪や反発心などへと変わり、凶暴な性質へと変化していったのではないかと想像できました。
このことは自分を抑えて生きてきた人についても当てはまるのではないかと思います。
この物語から無理やり何かの教訓を得ようとしたら、私の場合には本音や本質的に望んでいることを抑圧するのではなくて、社会的にも受け入れられる形で発露していく方法を模索する、という生き方へシフトするきっかけになるんじゃないかと思います。
まあ、とはいえ物語ですから、まずは楽しく読むこと、そしてこの世界観に没入して味わい尽くすことが大切であると言えるでしょう。