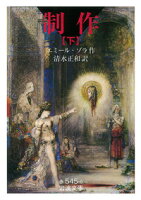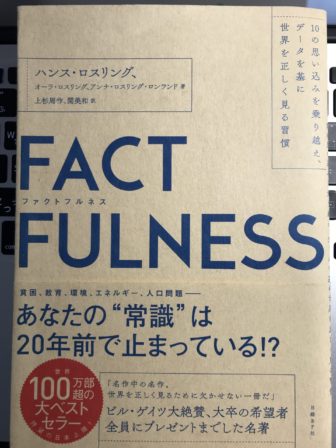制作(上・下巻) エミール・ゾラ著
エミール・ゾラの自伝的小説
本作はエミール・ゾラによる『ルゴン・マッカール叢書』と言われるシリーズ物の14巻という位置付けの小説です。ゾラ自身が「第二帝政時代における一家族の自然的・社会的物語」という副題をつけた作品群の一つで、主人公のクロード・ランティエもマッカール一族との血縁関係はあるようです。
本作下巻の巻末にある「解説」にて、
彼は『居酒屋』のヒロインであるジェルヴェーズ・マッカールと愛人オーギュスト・ランティエの間に生まれた長男であり、有名なナナ(アンナ・クーポー)の異父兄である。とはいえ、当作品は「居酒屋』や『ナナ』とは何ら直接的関連がない。独立した芸術界小説とみてよい。強いて共通点はといえば、主人公がいずれも悲劇的な死で終わるというぐらいだ。
このように説明されています。
作品上はほぼ関連はないと言っても間違いなさそうです。
何よりも本作がルゴン・マッカール叢書中の他の作品と異なる要素として、エミール・ゾラ自身の自伝的小説であるということもあります。
シリーズ中でも異彩を放っていると言えるでしょう。
また、作中でゾラ自身がモデルとなっているであろうサンドースという人物が、ルゴン・マッカール叢書を制作する計画にも思える構想を述べていることもあります。
この他、主人公のクロードはゾラと同郷のポール・スザンヌを、ボングランはエドゥアール・マネをモデルにしているのかと思うような描写がなされています。
しかし本作「解説」では、
ゾラがどのように画家クロードを描いているか。
「劇的に脚色したマネかセザンヌ、どちらかといえばセザンヌに近い人物」
作品準備段階でゾラがクロードについて記したメモである。
特に作品前半のクロードは、ゾラが親しく交わったセザンヌとマネを複合して作られたことは作品を読めば一目瞭然である。
というように、クロードの中にスザンヌとマネが存在するような人物として描かれています。
解説を読んだ後に本文を再読すると、このような意識を持って読むことができるので1回目とはまた異なる印象を受けます。
さらには本作品が、どのような意図で書かれたのかということも知っておくと、さらに作品を深く読み込めると思います。
本書の「解説」より再び引用します。
クロード・ランティエを通して、芸術家の自然との闘い、作品創造の努力、肉体を与え生命を生み出すための血と涙の努力を描きたい。それは常に真実との闘いの連続であり、しかも常に打ち負かされる天使との格闘である。つまり私はこの作品で、私自身の内密な創造の営み、絶え間なく苦しい出産を語るだろう。私はこの主題をクロードの悲劇の形で拡大誇張して示そう。クロードは決して満足することができず、自らの天賦の才実現できないことに激昂し、さいごには実現できない作品の前で自殺するのである。つまりゾラは、自らの体験から芸術家の「作品創造の苦しみ」を中心主題とし、それを画家クロードの悲劇で物語ることを意図した。
まさに芸術家の創作の苦しみを表現するために、クロードが徹底的に苦しんだ挙句に自殺する、という流れがそもそも意図されています。
クロード自身が作品の前で自殺することも、作品を生きているうちに完成させられない、天才的な画家を象徴的に表現しているような印象を受けました。
天才は認められなくても天才なのか
本作はクロードという天賦の才を持ちながらその作品が認められない画家が主人公です。
その才能の豊かさは仲間内のみならず、すでに評価され名声を得ている画家のボングランでさえも高く評価するもの。大衆にはまだ理解できない芸術の到達点とされています。
一方、クロードの作風を一部取り入れたファジュロールという人物は、世渡りが上手いこともあり、次第にサロンに評価されていきます。
ファジュロール自身もクロードの才能を認めており、自分は絶対に敵わないと自覚しています。そしてクロードの技法を真似して作品を制作しますが、能力の低さがかえって大衆に評価されてきます。さらにはここから、ファジュロールは上手く世渡りをこなすことで上流階級へ食い込み、サロンの審査員にもなっていきます。
このような本来評価されてしかるべき才能あふれる人物が辛酸を舐め、一方で能力は劣り天才の模倣で評価されていく展開に、読み手側はなんとも言えない無力感を感じます。クロードの日常も、絵を中心に次第に荒んでいく描写が、より生々しさを感じさせていきます。
芸術小説なのにリアルな人間臭さが充満している作品
若い頃(上巻での内容)には、まだ目が出る前の若き芸術家仲間だった登場人物も、それぞれが仕事が評価されたり家庭を持ったりと状況が変わる中で、お互いへの思いも変化します。
モデルとなったスザンヌも、パリを離れて田舎で創作活動に集中したように、クロードもパリを離れて田舎で生きること自体に対する喜びを見出しかけていきます。
ところがその天才性が人間らしい幸福へ浸ることを拒み、いつしかパリへ戻ること、絵画へ手中し命を賭けて取り組むことへと執着していくのです。
後半(下巻)では、クロードと結婚したクリスティーヌが絵のモデルとなって制作を助けますが、絵の中の女(クロードにとっての理想、創作活動)とクリスティーヌ(現実世界、人間としての幸福)の対立として、象徴的に描かれています。
絵の中の女に嫉妬するなど、普通に考えたら馬鹿馬鹿しいと思いがちです。
しかし本作を読み込んでいると、クロードの描く絵の中の女が、まさにクロードの心を鷲掴みにし、クリスティーヌ(現実の生活)を一切顧みなくなる情景が思い浮かびます。
最終的にクロードは作品の前で自殺を遂げてしまうのですが、彼にとっては自分自身の命を添えることで、やっと唯一と言っていいような大作が完成することになります。
また、後半部分では若い頃から仲間として付き合ってきたメンバーとの再開の場面も描写されており、同じように集まったはいいが状況や立場が皆違っているため、昔のように信頼し合うような関係性にはなれません。それを確認するために集まったと言ってもいいほど。
時間の経過とともにかつての友人たちと疎遠になってしまう、現実社会での余裕のなさもリアルに描かれているあたりが、やはり読者の共感を読んで引き込んでいきます。
その引き込まれるような危険な雰囲気が、まさにゾラの作品らしさというか、暗澹とした悲劇の匂いとして満ちてきます。
本作は狂気と天才性が共存する一人の人物が主人公として描かれている時点で、物語の終局にはきっと主人公は自殺するぞ、ということがわかります。
ある意味では、読み手の予想通りにことが進んでいくので、暗い中にも気持ちよさが存在します。
しかし、クロードの心情を事細かに追っている読み手にとっては、クリスティーヌと息子のジャックとも幸せに生活して欲しかった、というクロード自身にとっては幸せになり得ない結末も期待してしまう部分もありました。
読後感としては、そもそも主人公が自殺するだろう、という予測もたち、著者もそこをゴールとして構想していることから、悲劇的な終わり方をするにしては気持ちのいい感触が残っています。
やや長めの小説ですが、じっくりゆっくりと読んでいると、芸術家の熱い気持ちに寄り添って、自分も何か熱中していた頃の思いが蘇ってくるように感じる小説でした。