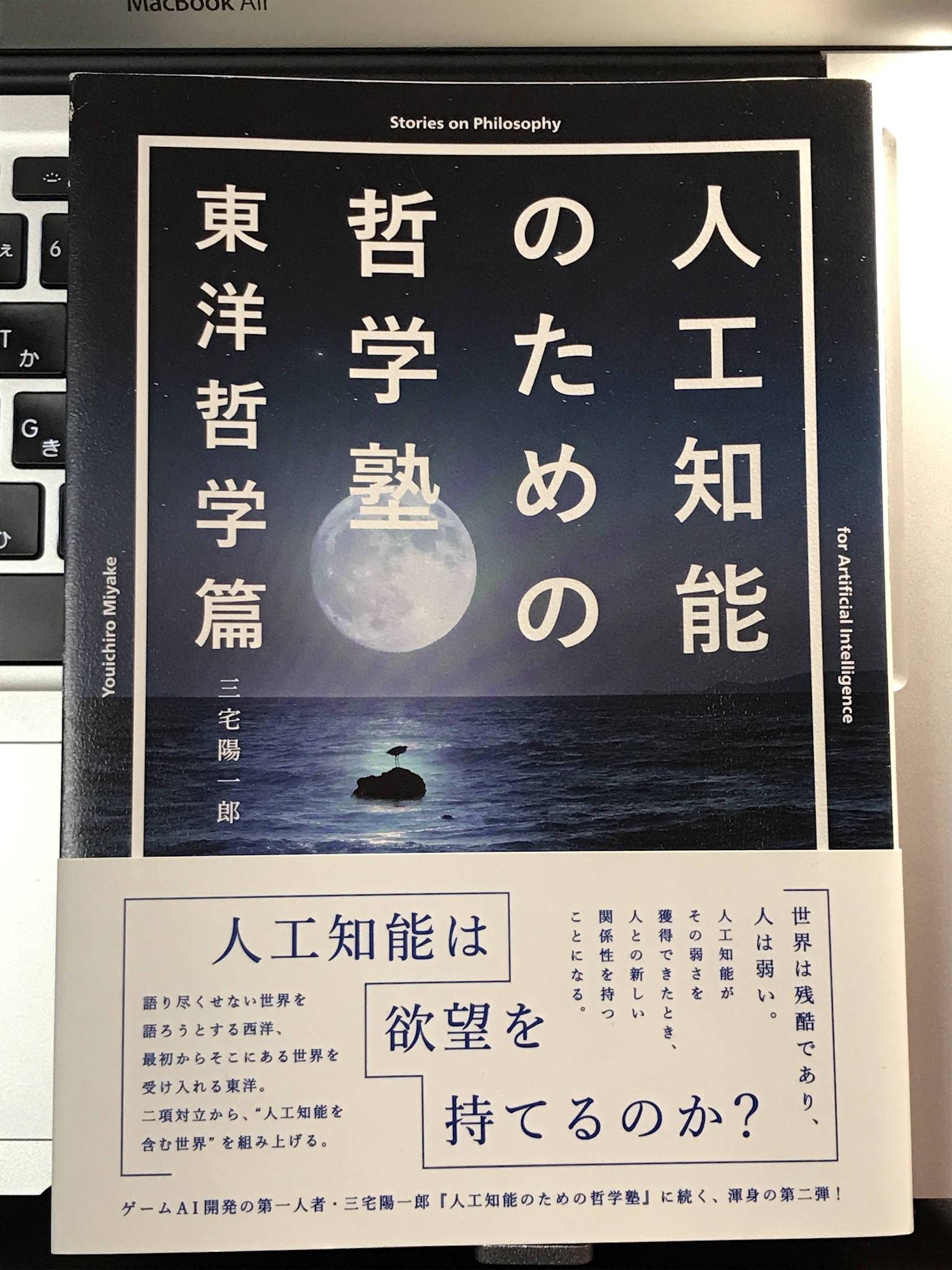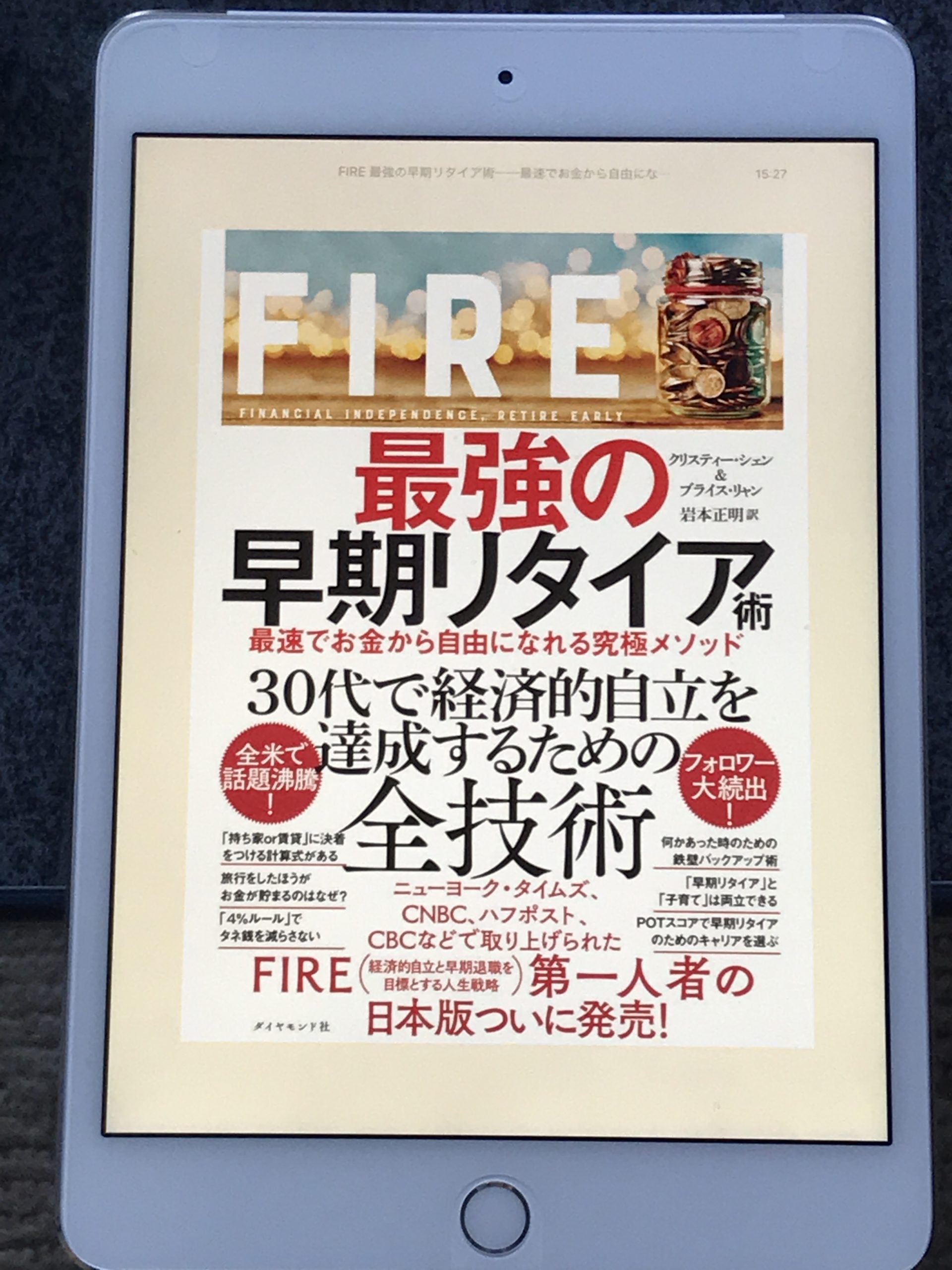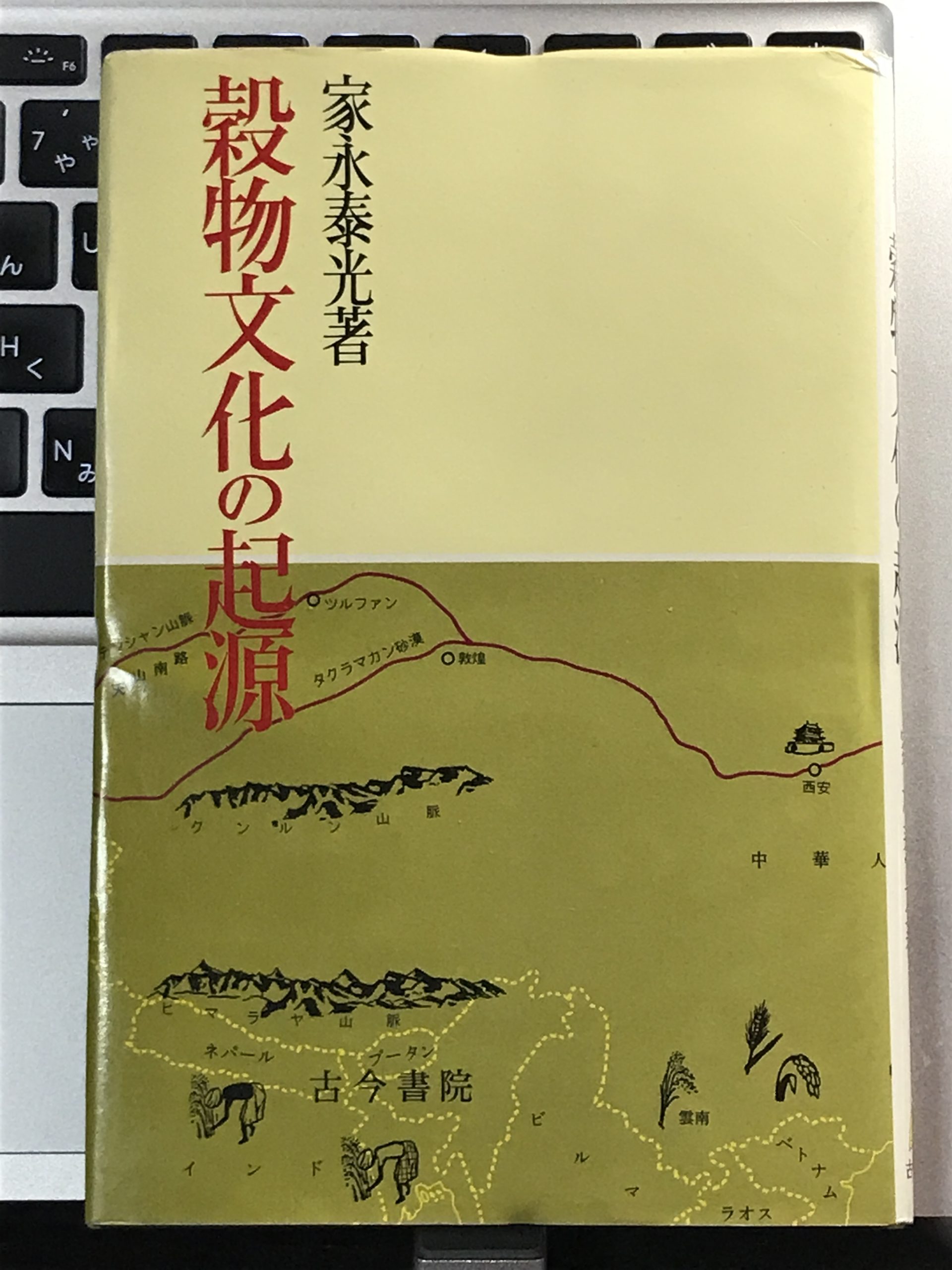『哲学対話』が積読消化のきっかけになった
この本は2018年4月に出された本で、実は書店で平積みになっていたのを衝動買いして積読の塩漬け状態に2年間もなっていた本でした。
人工知能の開発は従来の技術開発とは比べ物にならないスピードで進んでいる(と、思っている)ので、今さら2年前の本を読んでも仕方ない…そう思っていました。
しかし先日読んだ『ゼロから始める哲学対話』に触発されて、再び哲学的な頭の体操をはじめようと思ったこと、そして2年間のブランクを埋めるには2年前の本がちょうどよかろうということで読み始めました。
かなり分厚い(382ページ)上にちょっと本のサイズも大きいので、文字がビッシリ詰まっている印象。そんな見た目にも圧倒されての積読長期化でした。
読み始めて感じたことは、この本は「哲学塾」として講義が行われた内容を元に書かれているということで、非常に読みやすい形になっているな、というところでした。
久しぶりに読み応えのありそうな哲学書を手にしたので、これは私に取っては助かりました。
西洋哲学に対する東洋哲学の視点を取り入れる試み
肝心の中身ですが、この本は第零夜〜第五夜までの各論と、最後に総論として章分けがなされていて、それぞれ東洋哲学の視点から人工知能をどうやって作るのかを考えています。
この本が出る前に『人工知能のための哲学塾』という西洋哲学の視点を人工知能の開発に生かすための考察がなされた本があったようですが、今回はそれに対する東洋的な視点も取り入れてみようという試みのようです。
この時点ではまだ西洋哲学編は読んでいないのですが、本書を通読する中でも随所に誰々のこの考え方と似ているとか、この考え方とは対極的などど書いてあるので、知らなくても困らないようにはなっています。
でも深く理解するには、西洋的視点(世界と対峙)に対する東洋的視点(世界の一部)として把握することが重要だなあとは感じました(繰り返しですが、本書だけでもその視点は持つことができます)。
基本的に現在の学問体系は万学の祖たるアリストテレスが作った形、つまりは西洋哲学的視点に基づいた、分割して専門化する理解の方法がとられています。
従って人工知能という工学的技術の探究についても、当然ながら西洋哲学的な思考の枠組みが採用されていると言っていいでしょう。
しかしながら人間の知能(人工知能の雛形)とは、いまだにそのものの定義が決められず、全体像は一体どうなっているのか、そもそも潜在意識という不明瞭な深い領域までもが存在しており、完全なる認識には至っておりません。
そんなときに、西洋的視点だけのアプローチで、より完成度の高い”知能”と言えるものが作り出せるのか?という疑問が生まれます。
本書の著者はその部分に疑問を抱き、東洋哲学的な視点を取り入れてみようというとなったのです。
知能の形成に至る”禅”のプロセス
西洋的な知能の捉え方は、学問体系が分化・専門化していくように、要素の組み合わせで成り立っているとします。
一方東洋的な知能の捉え方は、全体の中の相互作用から生まれる、たまたま今ある状態のそのものを知能とします。
この全く異なる知能の捉え方にまず私自身が驚いたこともあるのですが、これを統合してより自然な状態に近い人工知能のモデルを作ろうとします。
それは、まずは現在わかっている知能を構成するあらゆる要素を組み込んだ、叩き台の人工知能を作ります。
そして人工知能に様々な学習(人間では体験にあたるもの)をさせ、成長させていきます。
そのままでは人工知能には欲望がないので、生き物の知能のような煩悩というようなものがありません。
この世界に対する執着がない(維持すべき身体が世界の中に存在しないから)ためです。
そこで「禅」の考え方を取り入れていきます。
禅とはこの世界に生存させ続けるための身体を持つ人間が、その生存欲求に基づく煩悩を断ち切って悟りを開くことを目指して行うものです。
元々、いわば既に悟りを得ている状態の人工知能に対して、そのままでは人工的であり不完全なままの状態である知能に対して、禅のプロセスを遡ることによる煩悩の獲得を目指そうとなります。
人工知能が”人工”らしさを残している限りは、それは今の不完全な、何かの作業を人間の代わりに行うだけの道具としての存在でしかありません。
しかし人工知能に、人間がもつ人間らしさとも言える煩悩を持たせることによって、より生き物の知能らしさを付与することができるので、ここへ来てやった「知能」であるということができるものが出来上がるようにも思えます。
”不完全さ”の付与は魂のようなもの?
これまで人工知能に関する書籍や情報に接する中で、なんとなく違和感というか知能といえないのではないか?という感覚がありましたが、この本を読んでそのモヤモヤが晴れたように感じました。
それは「人間らしさ」という不完全さ、なのかもしれません。
人工知能は所詮は機械であり命が宿っているわけではない、と私は思うのですが、もしその人工的に作り出された知能のようなものに、人間がもつ煩悩(この世界に対する生の執着)を付与されたとしたら、そのものは「生きている」と認識するかもしれません。
この本を読んでいるときには、哲学的な考え方やその思想を説いた人物がたくさん出てきて、いわゆる哲学書の難解な感じがあって眠くなることもありました。
そのせいか、著者の書いてくれた詳細な部分は記憶に残っていないのかもしれません。
その上で本書似たいする私自身の認識としては、人工知能に欲望を持たせることによって人間らしい人工知能が実現し、人間同士の自家中毒状態を緩和できそう、SNS疲れとか閉塞感を軽減できるかもしれない、ということです。
これまで私は人工知能が仕事を肩代わりしたり効率化してくれるものだとばかり思っていましたが、この本にある東洋哲学的な視点を取り入れた(欲望を持った)人工知能が生まれたら、それは人間同士の心理的距離を調整する役割を持つかもしれません。
通信技術の発達によって、人と人との距離が常時接続のような形になってしまい、それによってコミュニケーション疲れを感じている人が多いように感じます。
欲望を持っているかのように振舞う人工知能は作れるのかもしれませんし、発展途上ではそういうものを応用することもあるでしょう。
しかし最終到達点としては、人間にとっての煩悩と言えるようなものを持った人工知能が生まれることによって、より人間臭い、温かみのある人工知能の精神性が作りあげられることになるのではないかと思います。
その過程で人間そものの精神性の解明、その深みの理解へとつながるのではないかと思い、むしろそちらの発展も楽しみに思えてくる読後感を得ました。
人工知能のための哲学塾 東洋哲学篇 /ビ-・エヌ・エヌ新社/三宅陽一郎