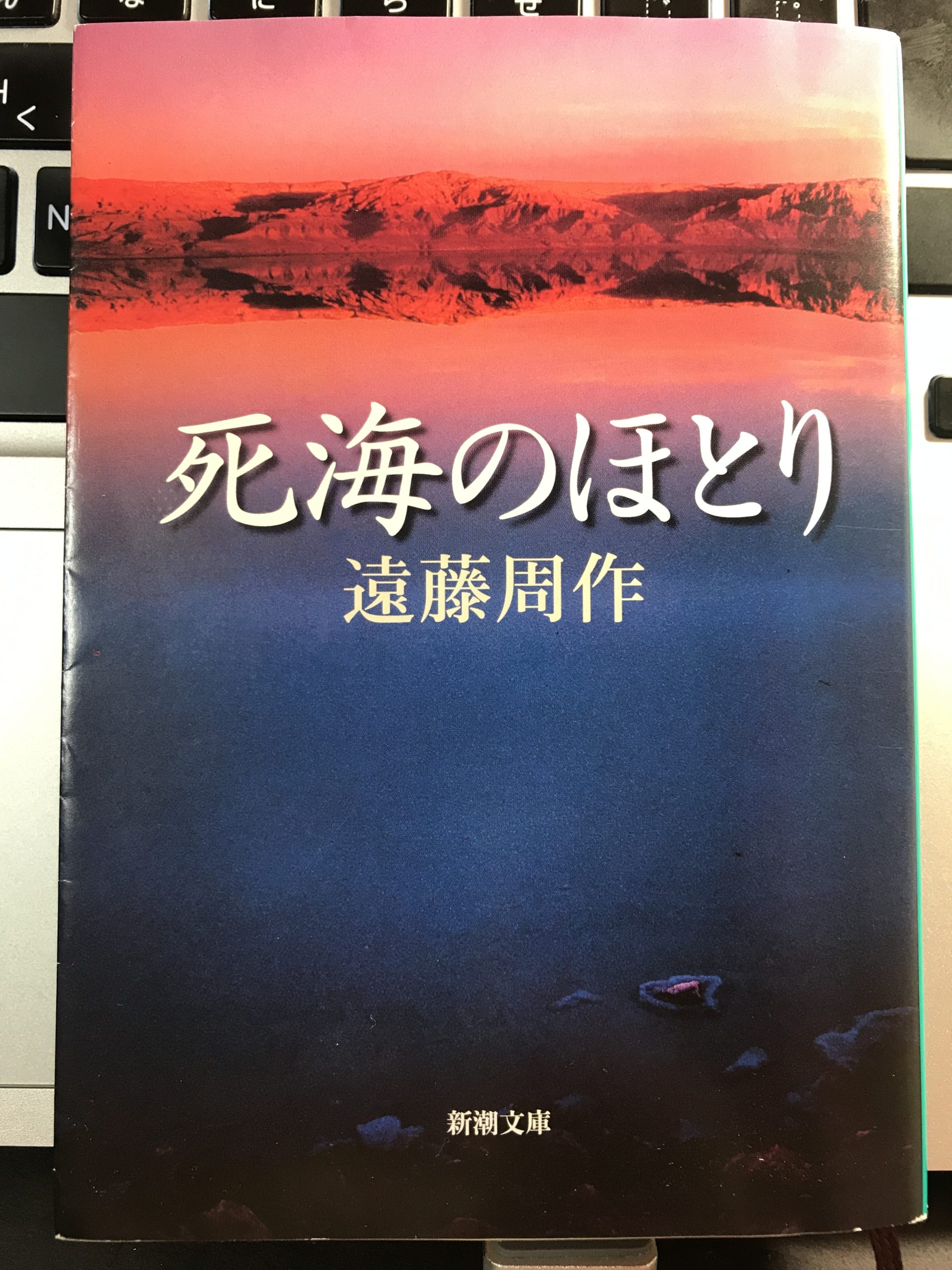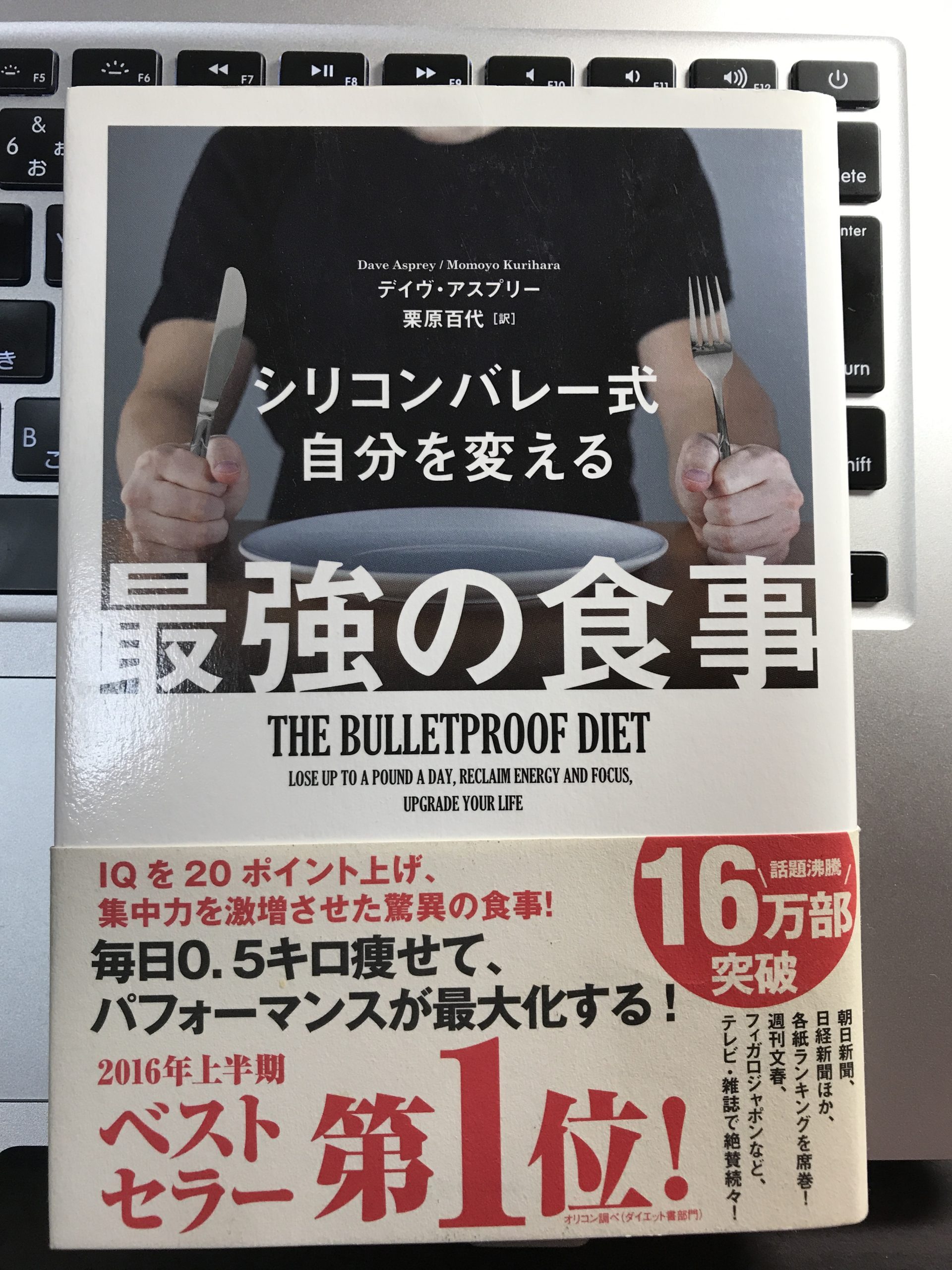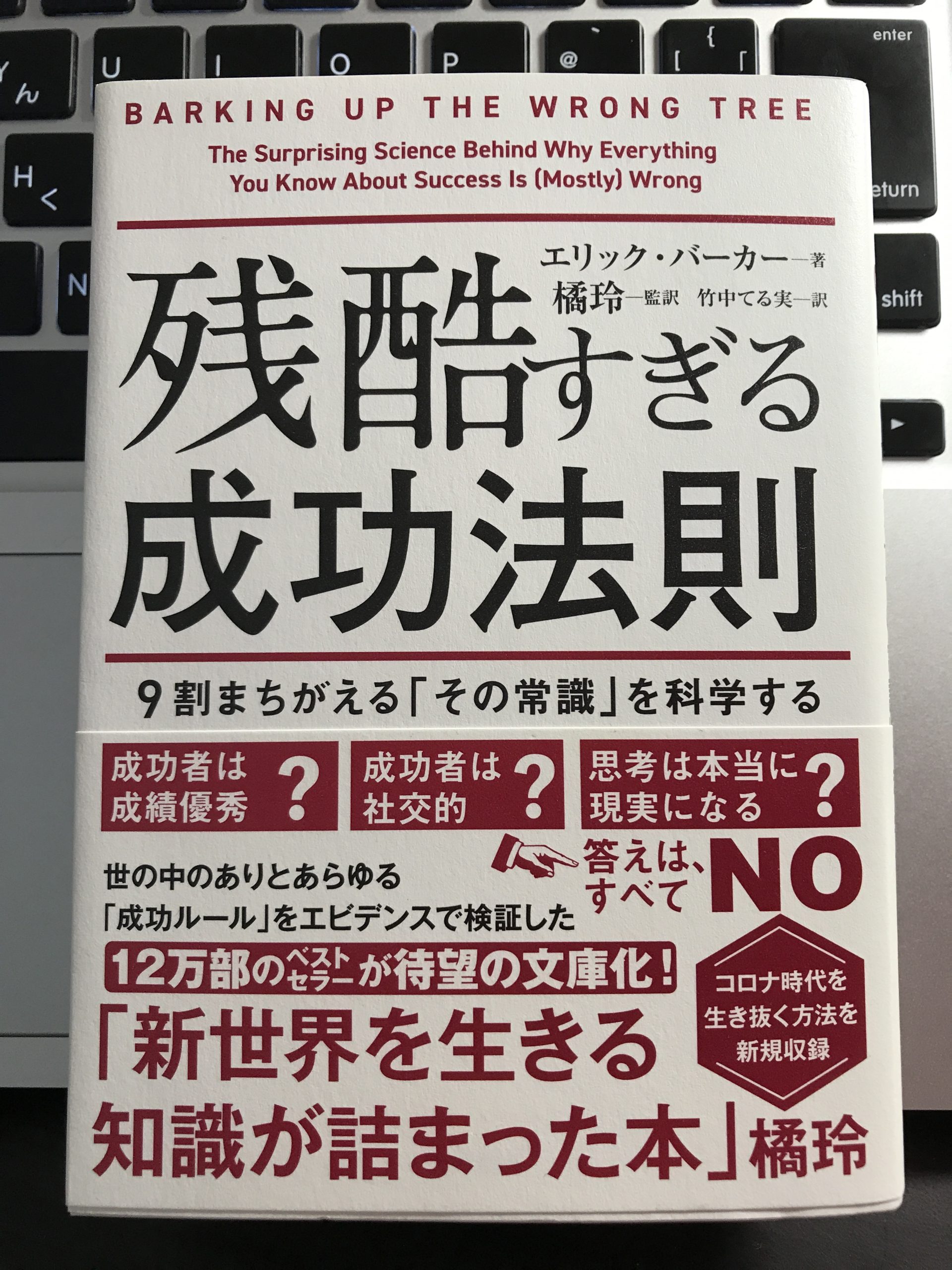生々しさの先の神聖さの表現
父性的宗教と言われそのように考えていた私自身も本書通読後に感じたのは、徹底的に「愛」
だけに生きた人間のイエスを描くことで、まるで人間のやることではない次元の愛を示し、
翻ってそこに「神性」とも言えるような清らかさを表現した作品であるということです。
この作品に登場する「私」と学生時代の友人である「戸田」は、信仰を深めようとすれば
そうするほどに信仰に対する疑いが生まれることに気がつき、聖地エルサレムの巡礼の旅に
出ることになった、という背景。
この小説を読む中で感じることは、キリスト教のいわゆる教会的な正式なもの(=作中に登場
する熊谷氏に象徴)に対し、キリスト教として形成される前の、生々しいイエスが何を目指し
何を成した(この作品では「為せなかったのか」のほうがしっくりくる)のかを追求していく
その姿勢です。
私信仰があるわけではないが、自分で望んで聖書を読んだ時には、やはりこの作品で示される
「ただ寄り添う」ことによって、現実世界では何もできない(具体的な利益として具現化し
にくい)「愛」というものを知らせて広めたのがイエスだと思うのです。
作中でイエスが、自分が横切った人生の主は、自分(イエス)のことを忘れない、というよう
なことをいいます。
これは熱病で瀕死の状態のときにイエスが寄り添ってくれたおかげ(?)で生還したアルパヨ
に代表される様に、こちら(ここではイエスに人生を「横切られた人」)は何度もイエスを
棄てても、あの人は絶対にこちらを見棄てることはない、という事実。
裏切り者に対しても、「裏切るが良い、あなたのその裏切る時の悲しみや恐怖も引き受ける」
という徹底的な許しで向かい合う姿勢。
聖書にもそういうようなことは書いてありますが、生々しい描写と合わせて説かれるこの話
は、より深く信仰が無い者にとっても心に響くものがありました。
2000年前のエルサレムには掃いて棄てるほどの自称「預言者」「救世主」がいたといいます。
その中ではかなりの実力者も存在していたはずです。
それでもなぜ今に名を残すのが、作中でも描かれている様な枯れ枝の様な見窄らしい体をした
弟子にさえ見捨てられた、惨めで「何もできない男」なのか
それは、この人(イエス)が何もできないのに人生を横切られた人々の心の中に残って、
奇跡はおろか何も出来ないのに誰よりも何よりも優しい人だった、と記憶されたから。
死に瀕しても恐怖に負けて騒いだり喚いたりせず、徹底的に神に自分を委ね、自分の死を
以て、苦しむ人や悲しむ人の重荷を引き受けようとしたから。
巻末の解説では、「永遠の同伴者」としてのイエスを描いた作品であると書かれています。
同伴者という表現が、まさにぴったりのイエスの描写であり、また実際の人間としての
イエスもまた、本作品のような愛の表出である同伴者としての側面があったのではないか、
そう思える読後感を残しています。
感想
母性的な文化の日本的感性によるキリスト教理解でいいのかわかりませんが、私はこの本を
読んでいる最中も、現在と過去を交互に描写される中で、過去のイエスが寄り添う行為に、
とても強いリアリティを感じました。
聖書の内容は、後世の教会関係者が、神性や権威性を付与するための脚色がある(作中の戸田
も言及している)と思いますが、聖書考古学の視点から見て、当時のイエスの状況を読み取る
ようにすると、フィクションの小説とは言っても、この作品に描かれているようなイエスとい
う人物の足跡が浮かび上がる様な不思議な感動を覚えたのが印象的でした。
遠藤周作の描くキリスト教や信仰、イエスという人物は表現の方法やアプローチが秀逸なのか
私自身が聖書を読んだ時に感じた現実離れした違和感の先にある、
「で、結局リアルのイエスはなにしたの?」という疑問に、1つの回答としての説を提示して
くれている様に思い、フィクションとは言え楽しく読むことができました。
ただキレイでスゴイ奇蹟を行える超人ではなく、汚くて見すぼらしく、何もできないイエスが
ただ愛を示し続ける、という行為にこそ私は神性というか聖なるものを見た気がします。
本当にこれだけのこと(ただ寄り添い手を握る)を貫き通した人物がいたとしたら、やはり
世界中に影響を及ぼすだけのインパクトはあるよなあとも思いました。