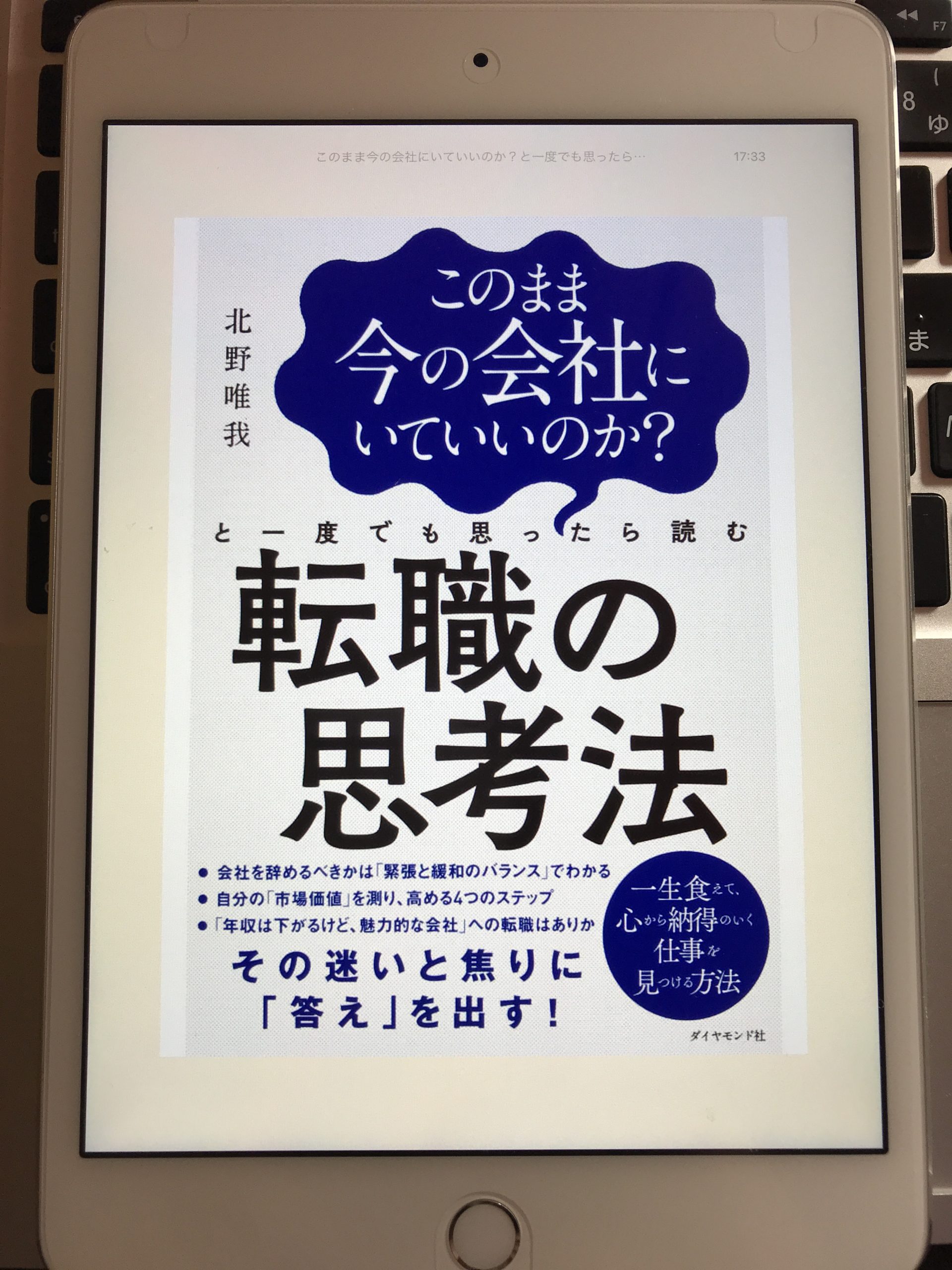イエスの生涯 日本人視点に仕立て直されたイエス像を描く試み
遠藤周作による信仰の深化と、日本人という立場でのキリスト者として受け入れるイエス像を模索した作品。
『死海のほとり』で触れていた「愛のみにいきた無力な人」としてのイエスを、聖書の物語と照らし合わせ、過去の「イエス像」に関する研究も織り交ぜながら描いていく試みです。
これは日本というキリスト教が生まれた地域とは大きく異なる環境で、私たち日本人の立場としてキリスト教を受け入れようとした時の葛藤を超えるためのきっかけになりそうな本です。
遠藤氏もあとがきでは、キリスト教というブカブカで違和感のある洋風の服を着せられて、最初は戸惑ったけれど簡単に捨てられるものではなかったし、それなら日本人にあうような和服に仕立て直してやろう、という気持ちで考えを深めていったようです。
聖書との対照もところどころに記載があり、深く理解したいとか本当に聖書にそんなことが書いてあるのかを確かめたい場合にはとても便利です。
そして聖書を側に置いて照らし合わせながら読むと、著者が引用した部分の前後の文脈もわかるため、より深く聖書の理解も本書の理解も進みます。
信者ではない人がそこまで聖書の中身を詳しく知ろうとは思わないかもしれませんが、遠藤氏が描き出すイエス、人間としてダメな奴だと人間社会で烙印を押されてしまうリアルなイエスを知ると、なんだか聖書もそこまで遠いものではなくなるような気がします。
究極の無力さが神性を宿す
イエスという、当時は別に珍しくもない名前で掃いて棄てるほどいる自称”預言者”の中でも、特に見た目はみすぼらしく、そして奇蹟が起こせず、ただ苦しむ人に寄り添うだけの人物の集団だけがなぜここまで世界的な宗教になり得たのか。
当時のユダヤには多くの預言者や教団が存在したといいます。
しかし他の教団は、弟子たちが師を神格化していません。
イエスの弟子たちだけが、師を神格化して世界中に広めなければいけないと強く、心の底から思い、行動に移しました。
その最初の頃、直弟子がなにかに覚醒して世界に福音を広めようと思った時のイエス像が、本書で描かれているイエスなのでは、と思わずにはいられないほどの「神性」を感じます。
それは究極的に何もできない、現実的にはなんの利益ももたらさない「愛」の実践です。
元々こういう母性的ですべてを許して包み込んでくれる思想があったからこそ、世界中の人々(あらゆる人が大なり小なりの苦しみを抱えたり罪悪感を持っている)が救いを求めたのではないかなあと思うのです。
そしてその愛を証明するために、裏切った弟子をはじめ誰に対しても恨み言を言わず、むしろ神に対して「彼らはまだ愛の表し方がわからないだけなんです」と庇う言動までし、そして誰よりも酷くて苦しい死を望みながら亡くなっていきます。
師を裏切った弟子たちがそのような師の最期の噂を聞いたりする中で、命が尽きるそこまでして愛を貫くなんて人間ではない!と衝撃を受けて、そして詳しは未だに不明な「復活」を経て、弟子たちが覚醒したのでは、と遠藤氏も一つの考えを示しています。
弱さを受け入れ、それを貫く強さ
本書を読み進めていると、これでもかというくらいにイエスが何もできなくてかつて称賛して群がった民衆たちが批難や暴力を加えるようになってきます。
彼らはイエスをメシア(救い主)として期待し、病人はその治癒を、民族主義者は独立運動のリーダーとしての役割を期待します。
しかしイエスはそうした人間の世界でのことには手をかさず、あくまで「愛」を実践した世界の理想の話をし続けます。
それは現実世界になにも及ぼすことがないものであり、「愛」というものが理解できない民衆や弟子たちは、次第にイエスから離れていきます。
それでもイエスは病人に寄り添い、娼婦に寄り添い続ける。
自分が考える理想を、どうしたら証明できるのか悩みながら、血のような汗を流しながら葛藤し続けます(こうした表現は聖書からの引用のようなので、また聖書を読んでみようかなという気持ちになります)。
最終的には政治的な意図から、ユダヤの治安を安定かさせるためのダシにされて処刑されてしまうイエスですが、それをも受け入れ、悪態をつかず、愛を証明しようと努めます。
十字架にかけられて絶命する時、「エロイ、エロイ、ラマ、サバクタニ(我が神、我が神、どうして私をお見棄てになられたのか)」という言葉を残したと言われています。
聖書に精通していない私たちが見ると、最後にはイエスといえども神に絶望したのだと思ってしまいがちな箇所です。私もそう思っていました。
しかし聖書の中身をよく知っている人、ここでは原始キリスト教が広めようとした相手なので当時のユダヤの人々ですが、彼らはいつも聖書を読む習慣があったため覚えているのです。
そんな彼らに向けて、聖書の一部を引用すると、その後に続く文言を書かなくても意図が伝わるのだそうです。それで聖書にはこれだけが書かれているといいます。
そしてこの言葉は旧約の詩篇22章からの引用なのですが、この部分は最終的に紙神への絶対的な信頼を表すものへとつながっていき、父なる神へすべてを委ねる、という言葉へつながっていきます。
こういうところが門外漢からすると大きな誤解をしやすいんですね。
この部分の話はキリスト教を信仰している方にとっては当たり前のことかもしれませんが、私のようなにわか聖書読みが知ると、もう感動してしまうような内容なのです。
聖書では、この言葉を言ったイエスを見た、処刑担当の百卒長が「この人こそ神の子だ」と言ったとか言わなかったとかとなっていますが、死ぬ間際に誰にも悪態をつかず、その上こんなこと言って死んだのではそう思うのも当然かな…と思います。
聖書は事実ではいが真実である
本書で印象的だったのが、遠藤氏による聖書の事実性への言及です。
聖書考古学という研究分野では、聖書の記述が考古学的に証明できるかを発掘や調査によって明らかにしていくのですが、中には事実とは違うのでは?という内容も書かれています。
聖書は一宗教の経典であって歴史書ではないのでそれは当然、といえるのですが、そこで遠藤氏は、聖書に書かれていることは、当時イエスに感銘を受けた使徒やその弟子たちが、広く人々に伝えたいと願った、という点で真実だと言うのです。
聖書には本当にことは書いてないとか安易に否定する人もいますが、これは歴史書ではなく教典であり、宗教観を表現するための書物です。
そういう聖書の存在理由から考えても、著者のこの考えは実に納得がいくものでした。
私自身、考古学や古代史が好きなので、聖書に書かれていることが考古学的に証明されたら、それはそれで知的に興奮するはずです。
でもそれは考古学という視点の話であって、キリスト教や神の子イエスとしての記述に関しては、聖書に書いてあることこそがキリスト者にとっての真実なのだ、ということです。
聖書を読む時のモヤモヤ(これはいったいどこまでが正確な記述なのだろう?)が、一気に解消されたような、それだけでもこの本を読んだ甲斐があったなあという考え方でした。
事前に聖書の流れを知っているとなお楽しめる
このような本を読む人が、聖書読んでないというのがそもそも稀なケースかもしれません。
しかしこの本は「イエスの生涯」というタイトルにもあるとおり、キリスト教創始のきっかけとなった人物に関する考察です。
したがって、その人の影響によって成立したキリスト教の聖書、そしてイエスが当然のように親しんでいたユダヤ教の視点を知るためには、旧約から新約に至る文章を読んでおくことが、よりよい理解につながるものと言えます。
ヨーロッパやアメリカでは基本的な知識として共有されている聖書ですから、ひとつの教養として読んでみるのもありかもしれません。
現在なら、Kindleなどで無料で読めるものもあるようです。
しかし私個人的には、聖書内の書物相互の関係を立体的に理解しながら読むと、物語としても楽しめるものですので、引照付き聖書を読むことをオススメします。
これを持っていれば、本当に信仰のある人からも一目置かれるかも?
聖書はいろいろな訳、そして各国語にも訳されているので、対照しながら言語の勉強にも使えそうですね。
ちなみに私は英語版とラテン語版も持っています。