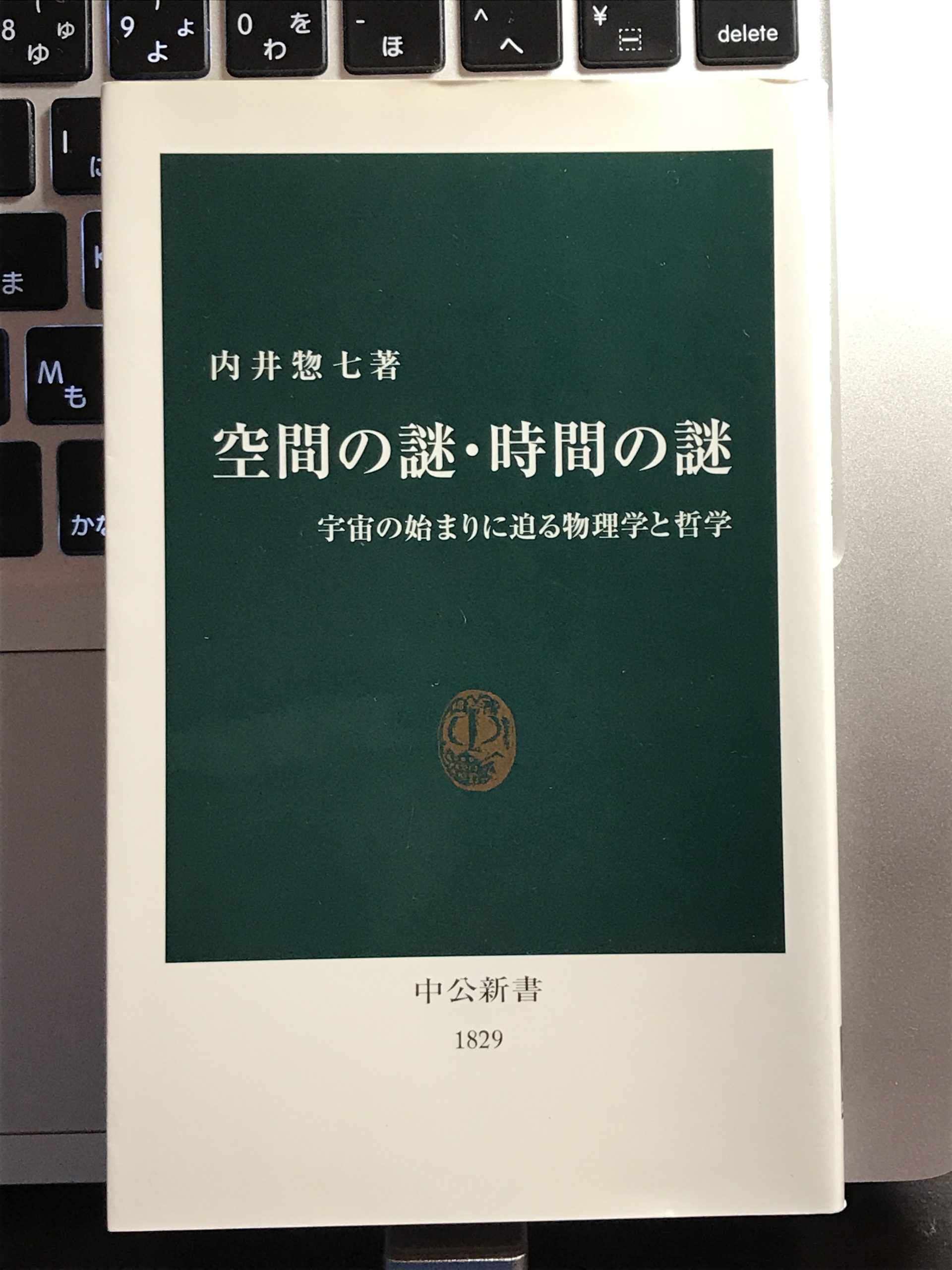「西洋哲学史」の決定版とも言える一冊
西洋哲学を学ぶ上で重要なのが、まず思想が作り上げられる歴史を学ぶことです。
哲学史を知っても哲学をしたことにはならない、なんて言われたりもします。
しかしまずは哲学とはどんなものなのか、どういうテーマについて考えられて、どのような仮説を経て、どうやって1つの思想として形成されてきたのか、それを知ることが自ら哲学することへの基礎力へとつながっていくと言えます。
そんなわけで西洋哲学史を学ぶ意義というのは非常に大きいのです。
そしてその重要度に比例するように「西洋哲学史」というタイトルの入門書は有名な哲学者の先生方のものも含めて、たくさん出版されています。
そのどれもが素晴らしい内容の本ですが、本そのものの読みやすさや読み手の習熟度などによっては、どの本を選ぶのかがとても大切になります。
高名な哲学者や先生が書いた本だから間違い無いだろう…と思いたい気持ちもあるのですが、すごい人が書いた本というのは、「教えることに対してすごい」人でも無い限りはとても難解な本になってしまいます。
従いまして、入門書という位置付けである西洋哲学史の本であっても、どんな著者のどんなスタンスで書かれた本なのか?を考慮して読む本を選ぶことが重要となってきます。
で、これらの「読みやすさ」「初学者も理解しやすい」「知識の網羅度」という点から本書は、とてもオススメとも言える一冊なのです。
この本が読みやすいという印象を受ける理由としては、著者が講義で話した内容を文字起こしして、形を文章に整えたものという理由があげられます。
話言葉は自然に頭に入ってきやすいですし、書き言葉よりも難しいことを丁寧に説明してくれる(説明の言葉が多い)傾向が強いように感じます。
一度通読するだけではさすがに完全に理解することは難しい(特に初学者の場合)ですが、話し言葉で書かれていることや説明が丁寧であることからも、繰り返して読み進めれば類書よりはかなり理解しやすい「西洋哲学史」の本です。
ソクラテス以前の哲学から始まる哲学史
西洋哲学史はソクラテスから始まる、という認識が一般的ですが、今回きちんと「西洋哲学史」の本を通読したことで、なんとなくぼんやりしていた「ソクラテス以前の哲学」についても整理することができました。
高校の倫理や哲学の授業でもソクラテス以前に世界を理解しようとした人々について触れますが、正直なところあまり存在感がありませんでした。
ところが本書ではソクラテスが現れるために必要なステップとして、タレスによる「すべての根源は”水”である」などの自然を理解しようとする思考の挑戦も紹介されています。
大人になってから改めて哲学史を学ぶことの意義は、なんとなく知っているけど複雑で苦手意識がある分野についても、テストや受験などのプレッシャーとは関係なく自分の知的好奇心にのみ依拠して学び直せるところだなとも思えるモノでした。
ソクラテスが「哲学の祖」と言われる理由も、この本を前から読んでいくと納得できます。
それは哲学が自然を理解しようとする観察と思考の試みから、人間とはなんなのか、幸せに生きるためにはどうするのがいいのかを考える形へと転換されたことが大きいと言えます。
いまでは哲学と言えば「いかに生きるべきか」を追求する学問であるという認識が広まっていますが、そもそも日常生活を営む上でそんな思考は全く必要ではありません。
日々の暮らしや生きていくことで精一杯だった時代から、思考にリソースを割くことができる時代へと変化していったことも、こうした哲学そのものの中身の変化から窺い知ることができるようになります。
プラトン以降の哲学はそれに注釈を加えているだけ
プラトン以降の哲学の発展を説明するときに、プラトン以降の哲学はプラトンがいったことに対して注釈を加えているだけだ、という風に言われることがあります。
それくらいプラトンが説いた内容はカバーする範囲が広く、また深い洞察がなされていたということでもあります。
そんなプラトンからのちの世代へと歴史を辿っていくと、なんとなくどこかで知っているような、聞いたことがあるような内容の細かい解釈を厳密に求めていっているようにも聞こえます。
本書のような西洋哲学の通史を読み通してみることでわかるのが、そういった哲学の歴史、思考の積み重ねが体感的にわかってくる感覚です。
とは言ってみたものの、そんな感覚が私だけの独自のものだったらなんか申し訳ない。
そうした体感的に得られるものも私は感服したところではありますが、個別の人物について認識を改めさせられたと感じたのが、エピクロス派と言われる快楽主義についてです。
なんだかこの一派の考え方、現在の日本(私自身もこの考えに近い)で広まりつつある思考に近いというか、その本質をついているかも…という印象を得たのです。
中世は暗黒時代なのか?
堺屋太一氏による『知価革命』で触れられていた、「現在は物質文明優勢の社会であり、それは中世を挟んで1つ前の物質文明であった古代との共通点がある」という視点を思い出しました。
だから現代人的視点で歴史を見てみると、中世は暗黒で古代のほうがより発展しているように感じるのでしょうね。
本書で記述されている中世の哲学的視点の変遷を追っていくと、まったく暗黒な感じではなくむしろ神について考えるために人間についての理解も深めようとしている、知的活動としてはかなり旺盛な印象を受けたりもするのです。
中世が暗黒時代で、ルネッサンスによって文化が復興したなんて言われていますが、これこそ現在の価値感(物質優勢)によるものの見方だなあ、とも感じられるのでした。
哲学史読んでいるだけなのに、他のことに関しても触発されるこの本、なんだか凄まじい存在感を放っています。
近現代になると専門分化されていく
近現代の哲学はもはや「なんだかわからないけど、なにやら難しそうなことを延々と考えている学問」という、かなり偏った認識を持っています。
そしてその認識は、本書を読むことによって多少は整理されていく感覚は得られるのですが、西洋哲学史全体として見た時の近現代の哲学はとても細かい部分の正確性を高めていくようにも受け取れました。
先述したような、プラトン以降の哲学はすべてそれに注釈を加えたもの、という認識をより確かなものにするように、プラトンが描いた大きな枠組みの中の細かい部分を、より正確に、より厳密に理解していく試みだという風に感じるのです。
そんな風に西洋哲学の全体像をなんとなく掴んだ後に現在の最先端(と、言っても本書が書かれてから時間がかなり経っていますが)の考え方に触れると、なぜ今その問題があるのか、そしてどのようなアプローチをしているのかの根拠から理解できるようになる気がします。
ただなんとなく難しそうで自分に直接関係なさそうなことだという認識から、古代の哲学から順を追っていくことで自分も歴史とともに成長できている、そんな不思議な読書体験になっていたのでした。
こんな体験ができるが故に、この本は数ある哲学入門書、西洋哲学史の中でも、多くの人がこぞっておすすめする一冊なのだなと理解しました。
あくまでも私なりの理解ですが。
なので、なにかのご縁でここに辿り着き、そして最後まで読んでしまったアナタもぜひ本書を手にとって読んでみてください。
哲学史から入る哲学は、自分自身の思考を鍛えるための基礎体力を身につけてくれること間違いなしです。