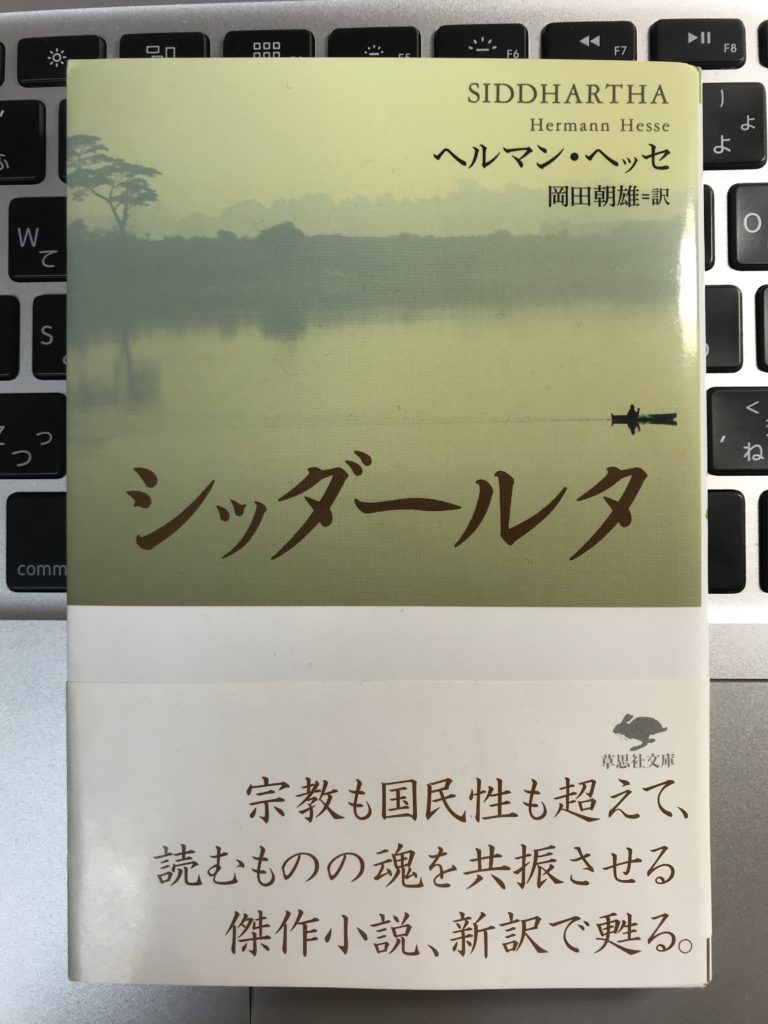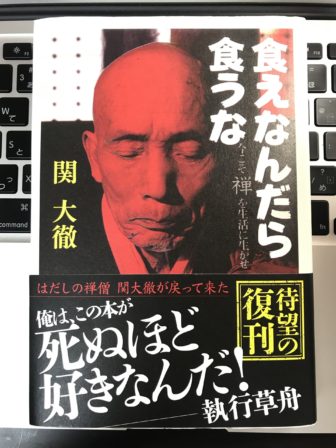シッダールタ ヘルマン・ヘッセ 著
悩める現代人のための叡智の書
本書は1922年に発表された当時、
ヘンリー・ミラーをして「世に認められている仏陀を凌駕するひとりの仏陀を創り出すこと、それは前代未聞の業績である。…『シッダールタ』は私にとって『新約聖書』よりも効き目のある薬である」と賞賛させ、20世紀ヨーロッパ文学の中でも最も多く読まれ、最も大きな影響力を持つ作品の一つとなった。
-本書カバーより一部引用-
との評価を得るほとに社会に影響を与えた本です。
また、本書の帯には
「宗教も国民性も超えて、読むものの魂を共振させる傑作症せる、新訳で甦る。」
とあり、いかに本書が多くの人に影響を与え、読み継がれてきたかを表しています。
著者・訳者について
ヘルマン ヘッセ(著者)
1877〜1962年。ドイツ、ヴェルテンベルク州生まれ。詩人、作家。一九四六年ノーベル文学賞受賞。代表作に『郷愁』『車輪の下』『デーミアン』『荒野の狼』などがある。岡田 朝雄 (訳者)
一九三五年東京生まれ。東洋大学教授。著書に『ドイツ文学案内』『楽しい昆虫採集』(共著)、訳書にヘッセ『蝶』『色彩の魔術』、F・シュナック『蝶の生活』などがある。-amazonより引用-
ヘルマン・ヘッセはノーベル文学賞を受賞した世界的な作家ですが、私が初めてこの方の本に
触れたのは、『ヘッセの読書術』(草思社文庫)でした。
だから元々はなんかたくさん本を読む人なのかなあ、くらいで、先入観なく読めたのが本書の
通読には良い影響があったように思えます。
本書をこれから読もうとする方も、著者がすごい人だったんだ等の意識をせずに、素直な
気持ちで読まれると、得るところも大きなものとなります。
本書の内容について
もうひとりの「仏陀」の魂の遍歴
本書はまるで本当の仏陀の成長過程を表しているかのような進み方をします。
読んでいると思わず、この本は史実に基づいた本だっけ?と混乱しますが、
本書は創作です。
本書の主人公シッダールタは、きっと仏陀と同じように人生のあらゆることに悩み、そして
乗り越えようとしたのだと思います。
仏陀自身もひとりの人間であり、その存在が当然背負うであろう悩みを乗り越えるために
厳しい修行を行ったのだと思われます。
本書では、シッダールタと友人が、教えを乞う相手として仏陀らしき人物が出てきます。
しかしその教え(=覚り)は、人から教えを聞いて得られるものではないような気がして、
シッダールタはその人物の元を去ります。
そして自らの体験として、様々な出来事を乗り越え、ついにはそれらしき体験を得ます。
これは悟りについての認識を、かなり正確に捉えているのではないかと思われます。
禅の書籍などを読んでいると、一見無駄な動作をさせられたり、いわゆる禅問答などという
行為が繰り返されます。
その行為によって何かを得るのではなく、行為そのものが成果であり答えであるということ
に、体感的に至る手段だとも言えます(『食えなんだら食うな』が参考になります)。
覚りを得る=体験的にしか知覚し得ない
本書を読む過程で、主人公のシッダールタが真理の探求について一切妥協しない姿勢が
とても印象的でした。
それ以外のところでは普通のひとりの人間として、むしろ人間臭い感じがとてもあって、
親しみすら感じるほどです。
本書の主題は「魂の遍歴」で、シッダールタその人が様々な試練の末に知覚することが
できたもの、それに至るプロセスと、その得たものは、外部からは提供し得ないんだ、と
いうことが強烈なほどのメッセージとして伝わってきます。
ネタバレになってしまいますが、ブッダと思しき指導者についていくことにしたシッダールタ
の友人が、数年ぶりに再開した時にいまだに他力本願、その指導者の教えがなければ何も
考えず、得ようとせず、もはや指導者なしには何も得られない状態になるほど依存している
状態も描写されています。
これは史実上の仏陀亡き後、弟子たちが師の教えに従わずに文字に残したり、教えの根本的な
部分を自分たちで会得できていなかったことに気づいていなかったのでは、という危惧にも
通ずるものでした。
今となっては何が本当の教えなのか、確かめる術もなければ、確かめられたとしても、誰が
それを答えとわかるのか、という問題もあります。
長い歴史の中で多くの覚者がなしてきたことを積み上げ、その結果を覚りとする。
その覚りとされたものを得るには、自分で体験的に知覚するしかない。
そんな事実が、まだ未体験のはずなのに体験的に理解できるんだ、という不思議な理解が
本書読了後にはもたらされます。
本書をオススメする人
これから社会に出る学生や、世の中の理不尽なことに疲弊している人にオススメです。
本書は物語の形で覚りを得るプロセスを追いかけています。
まさにシッダールタの魂の遍歴です。
若い時に読んでも「まあそういうもんか」で終わるかもしれません。
しかし若い時にこういうことを頭に入れておくことが重要で、何か壁にぶつかったりした時、
改めて読み返すと救いになる本です。
書評まとめ
本書は3回ほど時間を置いて読み返していますが、その都度、自分の状態が成長している事を
感じられる本でもあります。
人生経験が大事、と方々で言われますが、まさにその通りなのです。
漫然と生きているように思えて、毎日の仕事や人間関係など、日々私たちは大なり小なりの
試練に向き合っています。
そうした事例がたくさん集まることが、端的に言えば人生経験を積むということです。
そういう認識に至った時に、本書に対する認識も固まってきました。
仏教が救いになりうるというのは、最後の拠り所として自分が在る、ということに収束する。
自分が居る、ここが全てのスタートになります。だから仏教では死後の世界を否定します。
そしてあらゆる所有なども否定します。それは自分そのものではないから。
しかし世の中では所有や所属が拠り所とされ、生活を楽にするはずのものが、返って自分を
苦しめる元凶にもなってきます。
おそらく数千年前のインドでも今と同じような悩みに苦しむ人が多くいたのだと思います。
人間の悩みの本質(所有などの執着)を見抜いたからこそ、いまだに仏陀の教えが継承されて
居るのだなあと、自分なりの結論が得られた本でもあります。